日本癌学会主催 第24回日本癌学会市民公開講座 講演3「がん免疫療法の最前線」
玉田 耕治 先生(山口大学大学院医学系研究科免疫学分野 教授)
外科療法、化学療法、放射線療法で治せないがんを免疫療法で撲滅する
年間35万人もの人ががんで死亡しています。 一般的に行われる外科療法(手術)、化学療法(抗がん薬)、放射線療法では治らないがんがあるのが現実です。 私たちの体にはもともと免疫が備わっており、外敵から身を守ってくれています。その免疫力を使ってがんを攻撃し、現在治らないがんを撲滅しようというのが「がん免疫療法」です。 数十年前から、さまざまな研究が行われてきましたが、最近の研究の進歩は目覚ましく、標準治療として承認される薬も出てきました。
免疫とは、病原体やがん細胞などの異物を排除するもともと体に備わった機能であり、異物を感知すると、免疫機能を担うさまざまな白血球が体内で活躍を始めます。
まず、樹状細胞が異物を取り込んで分解し、「正常ではない」という目印(抗原)を出して、攻撃命令を出します。 抗原を見つけたヘルパーT細胞は、キラーT細胞と呼ばれる細胞を活性化させて、標的となるがん細胞を殺すために攻撃を仕掛けるのです。
T細胞はT細胞受容体という部分で異物を感知して、別の受容体からの刺激性共シグナルと抑制性共シグナルのバランスによって、異物が攻撃対象かの判断をします。 車の運転に例えると、T細胞受容体がエンジンを作動するキー、刺激性共シグナルがアクセル、抑制性共シグナルがブレーキに当たります(図1)。
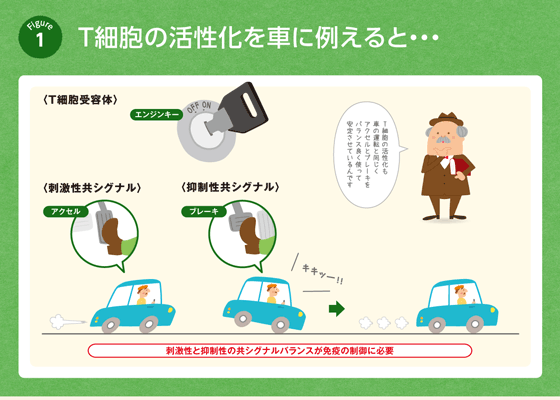
がんを標的に攻撃するキラー細胞を増やす
免疫力を利用したがんの治療法には、どんなものがあるでしょうか。
一つは、がんの目印を認識し、がんを専門的に攻撃する「がん特異的キラー細胞」を増やす方法です。
古くから行われている治療法に、養子免疫療法があります。 がんの患者さんのT細胞は活性化しているだろうという推測のもと、患者さんからT細胞を採取し、体外でさらに活性化・増殖させた後、体内に戻し、免疫反応の増強を狙う方法です(図2)。
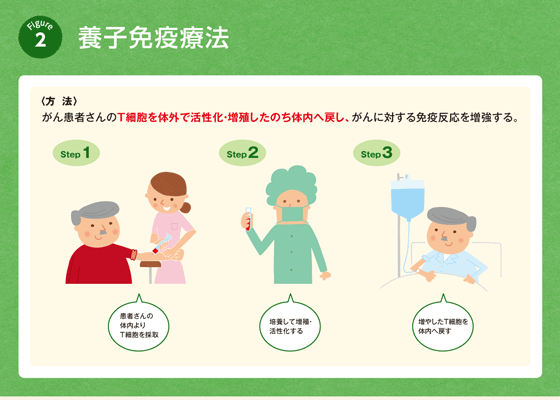
また、人工的に合成した「がん抗原ペプチド」をがんの目印として注射することで、キラーT細胞にがんの攻撃を促すがんペプチドワクチン療法も比較的古くから取り組まれていますが、いずれの方法も現時点では標準治療として確立はしていません。
免疫にかかっていたブレーキを解除
最近になって、がんの患者さんの体内ではがんに対する免疫システムが抑えられていることが分かってきました。
免疫反応を潜り抜けてきたがん細胞は非常に賢く、巧妙な細胞です。 攻撃を仕掛けても「何とか生き残ろう」と、本来は出るはずのない免疫反応にブレーキをかける物質の発現を促し、活性化しようとするT細胞を抑え、攻撃から逃れようとしていたわけです。 養子免疫療法やがんペプチドワクチン療法で思った通りの効果が出なかったのもこのためです。
ならば、免疫に急ブレーキをかけている状態(免疫チェックポイント)を取り除けばアクセルが効いて進むという発想が、ここ3~5年のがん免疫療法の急速な進歩につながりました。
ブレーキ役になっていた物質は、PD-1、PD-L1と言われる分子です。 その機能を抑えてしまう薬(抗PD-1抗体)を投与し、ブレーキを外し、T細胞を活性化し、がんを殺してしまおうという方法です(図3)。
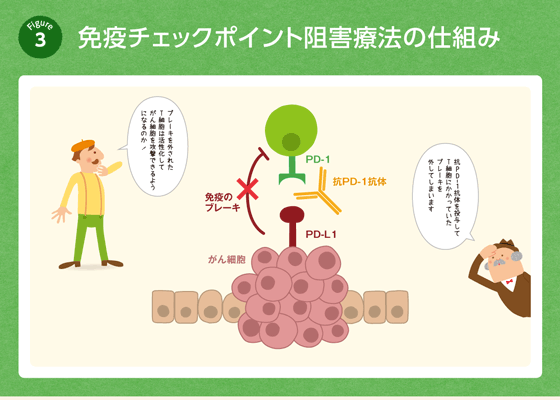
実際、抗PD-1抗体の投与によって、皮膚がんの一種であるメラノーマ(悪性黒色腫)、非小細胞肺がん、腎細胞がんが進行した患者さんの20~30%でがんが消えるなどの効果が認められています。
一方で、10%前後で発疹や下痢、間質性肺炎などの副作用も確認されていますが、免疫療法の場合、一度治療効果が出ると、効果が長く続くという特徴を持っています。
この治療は2014年7月に日本で初めて手術ができない進行期のメラノーマの標準治療として認可され、同年9月には米国でも承認されています。
遺伝子組み換え技術を利用した最先端の免疫療法にも期待
最先端の免疫を利用したがん療法として、遺伝子改変T細胞を用いるものも登場してきています。
急ブレーキがかかり、壊れた車のような状態にあるがんの患者さんの免疫システムの代わりに、遺伝子組み換え技術を利用してもともとがんとは全く関係のないT細胞を、がんを攻撃する細胞に作り替えてしまう治療法です。
まだ研究段階ではありますが、臨床応用を目指して、多くの研究や臨床試験が世界中で進行中です。 がん細胞を殺す能力がない通常のT細胞を、遺伝子操作によりがん特異性T細胞にすることは、普通の飛行機を高性能ミサイル搭載の戦闘機に改造するようなもので、がんを狙い撃ちにする高い治療効果が期待されています(図4)。
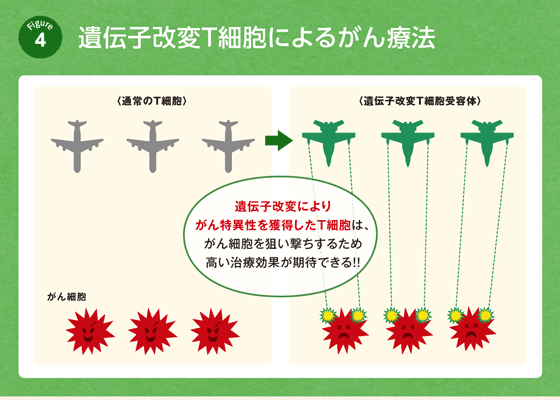
(企画・制作:あなたの健康百科)






