日本癌学会主催 第24回日本癌学会市民公開講座 講演1「肥満とがん」
原 英二 先生(がん研究会がん研究所 がん生物部 部長)
肥満はたばこと並ぶがんの原因
肥満が糖尿病や心筋梗塞、脳卒中の原因になることはよく知られていますが、がんにとってもたばこと同じくらい良くないことが分かってきました(図1)。
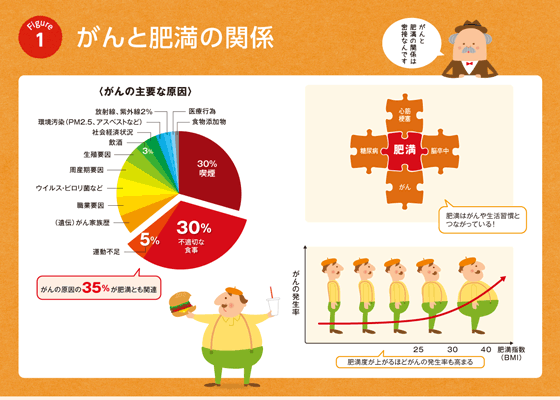
最近報告された英国人524万人を対象にした追跡調査によると、22種類のがんのうち17種類のがんは肥満するほど増え、特に大腸がん、肝臓がん、胆嚢(のう)がん、膵臓(すいぞう)がん、子宮がん、腎臓がんなどは肥満の影響を受けやすいことが分かってきました。がんにならないためには、たばこを吸わないことと同じくらい、肥満しないことが重要だといえるのです。
1日に必要なエネルギー量を把握することが大切
肥満を防ぐためには、適度な運動をすることとともに,適切な食事を取ることがとても大切となります。
まずは、自分の1日に必要なエネルギー量を知ることです。デスクワークが主の人ならば体重1キロ当たり25~30キロカロリー、立ち仕事の多い職業ならば30~35キロカロリー、力仕事をしている人ならば35キロカロリー以上が目安となります。この値に自分の標準体重をかけたものが1日に必要なエネルギー量です。
もちろん、自分が食べたもののエネルギー量を知ることも大切です。厚生労働省の公式サイトに、「肥満を防ぐ食事」としてさまざまな食品のカロリーが紹介されています。三度の食事はもとより、お酒やお菓子などもしっかり加えて計算してみましょう。1日に必要なエネルギー量に収めることはなかなか難しいことに気づくのではないでしょうか。
案の定、肥満人口の増加は、街中においしいものがあふれ、交通の便利な先進国が共通して抱える課題となっています。
人間の身を守る「細胞老化」はがんの原因にもなる
現状では、余分に取ったエネルギーは運動で消費するほかありません。しかし、少し虫のよい話になりますが、ある程度太ってもがんを発症しにくくする方法の開発を目指した研究が進められています。
そのためには、肥満になるとなぜ、がんのリスクが高くなるかを知る必要があります。そこで私たちが着目したのが「細胞老化」の存在です。
私たちの体は約60兆個の細胞で作られています。このうち一定の数の細胞は毎日分裂を繰り返して増殖し、体を維持しています。中には分裂を繰り返すうちに細胞が傷つくこともあります。この傷ついた細胞が増殖するとがんの発生につながるため、人間の体内ではこうした傷ついた細胞の増殖を停止する機能が備わっています。これが細胞老化です。
傷ついた細胞の増殖を停止する細胞老化は、人間にとって好ましい現象と考えられてきましたが、最近になって良いことばかりではなく、時間がたって、体内に老化した細胞がたまると、炎症反応やがんの発生につながる分泌性のタンパク質を生み出す「SASP」という現象を起こすことが分かってきたのです。そして、このとき生み出されるIL-6、PAI-1という物質は、肥満に伴って分泌される物質でもあります(図2)。
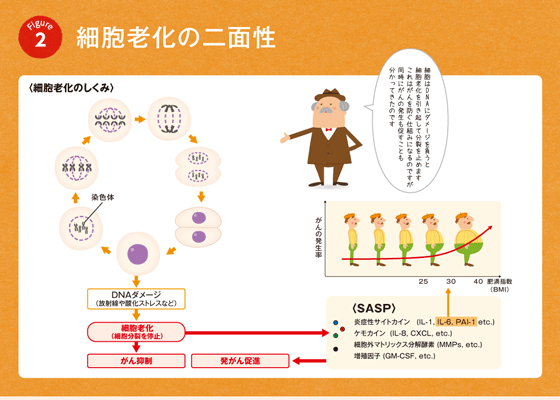
肥満すると増える二次胆汁酸が細胞を傷つける
生まれてから一度だけ弱い発がん物質をさらした実験用マウスに30週間、普通の食事または高脂肪の食事を食べさせたところ、高脂肪の食事を取って肥満になったマウスの肝臓で細胞老化が起こり、100%の確率で肝臓がんが発生しました。これに対し、普通の食事を取ったマウスでは1匹も肝臓がんを発生していませんでした(図3)。
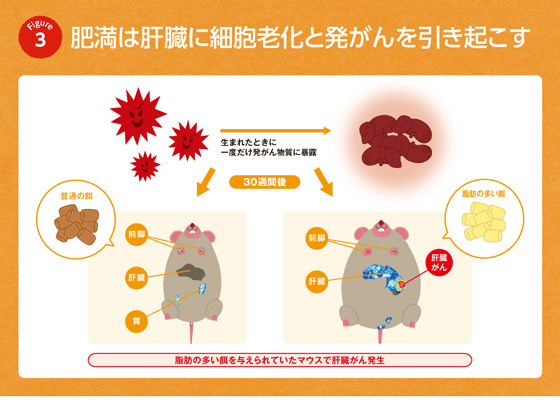
肥満になると、がんの発生を促すといわれている「二次胆汁酸」をつくる菌が腸内に増え、作り出された二次胆汁酸が血管を通して肝臓に運ばれ、肝臓の細胞を傷つけてSASPを起こし、肝臓がんを発生させることが分かってきています。
実際、抗生物質を与えて腸内のこの菌を退治すると、肥満になっても肝臓がんの発生が少なくなることも明らかになっています(図4)。これらは動物実験の結果ですが、人間も高脂肪の食事を取ると二次胆汁酸が増えると報告されています。
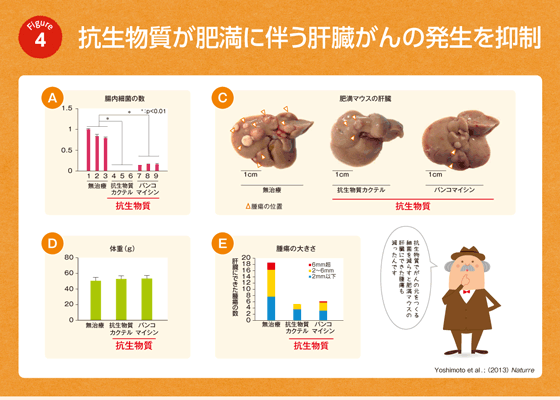
通常、脂肪肝は肝硬変を経て、肝臓がんとなりますが、アルコールを原因としない非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)と呼ばれる、肥満者に多く見られる肝臓の病気では、肝硬変を経由せずに肝臓がんになることがあります。
私たちが調べてみたところ、NASHから突然、肝臓がんになった人の肝臓の細胞では、細胞老化とSASPが確認できています。現在、こうした患者さんの協力を得て、糞(ふん)便の中にある二次胆汁酸を生み出す菌を調べているところです。
将来的に、検便で二次胆汁酸を生み出す菌の測定が簡単にできるようになれば、自分のおなかに抱えている発がんの危険性が分かるようになり、食習慣の改善に役立てることもできますし、その菌の増殖を抑える食品素材を見つけられれば、多少肥満してもがんが発生しにくい食生活が実現できるようになるかもしれません。そんな未来を描いて、研究を進めています。
(企画・制作:あなたの健康百科)






