第23回日本癌学会市民公開講座 講演4「乳がんの再発に関わるがん幹細胞」
後藤 典子 先生(金沢大学がん進展制御研究所分子病態研究分野教授)
20年たっても再発する乳がん
乳がんは、日本人女性の20人に1人が生涯に一度はかかる、女性の罹患(りかん)率トップのがんです。
早期発見ができ、良い治療法もあるので、乳がんが分かった後の生存率は他のがんより優れています。乳がんになったからといって死ぬことは、現在ではあまりなくなっているといえるでしょう。他のがんと同じく、進行していれば死亡率は高くなりますが、進行がんであっても適切に治療を受ければかなりの効果を期待できます。
ただ、高齢化や食生活の欧米化といった要因が絡まって、乳がんにかかる人の割合は年々増えており、それに伴って乳がんによる死亡数も増えています。
良い治療法があるにもかかわらず、なぜ死亡数が増えているのでしょうか。
それは、乳がんの場合、再発の可能性が高いからです。肺がんなど他のがんでは、治療終了後5年、10年とたっても再発がなければ、しばらくはある程度がんのことを忘れて暮らせます。ですが、乳がんは治療が終わってから10年、20年がたっても再発することがあるのです(図1)。再発部位は骨や肺、リンパ節が多くなっています。
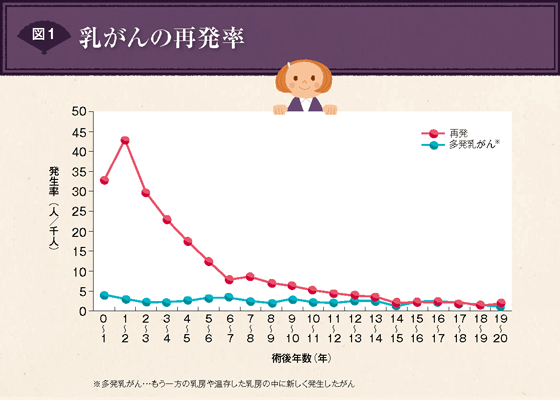
なぜ、これほど時間がたっても再発するのか。その理由が「がん幹細胞」の存在にあるのではないかということが近年、分かってきました。
乳がんの再発は「女王蜂」の再活性化
従来、がんは正常な細胞のDNAに傷が入ることで悪いがん細胞に変質し、その後、異常なスピードで増殖していく病気だと考えられてきました。増えた細胞がさらに増殖していくという、ハエの増え方と同じイメージです。従来の抗がん薬は、このようにどんどん増殖する細胞を死滅させる目的で開発されていました。
しかし、近年の研究の進展で、いわゆる「幹細胞」というものががん組織にもあることが分かってきました。幹細胞というと、全ての組織細胞を作り出せる力(万能性)を持ったiPS細胞やES細胞を思い起こす人も多いでしょう。単なる「幹細胞」にはそこまでの万能性はないのですが、体の中には脳神経や血液細胞、乳腺の細胞といった特定の組織にしかならない「組織幹細胞」があることが明らかになったのです。
組織幹細胞は、自分で増えるだけでなく分化すること(違う性質を持つこと)もできます。幹細胞が分裂して2つの細胞(娘細胞)になると、1つは母細胞と同じ多能性を持った幹細胞に、もう1つは組織を作るのに適した細胞になるのです。この性質は、がん細胞になった場合もある程度保たれます。そうしたことがここ10年ほどの研究で次々に分かってきました。
現在では、がん化した組織幹細胞ががんの成り立ちに関わっているという考え方が主流になっています。通常の組織幹細胞は、幹細胞の増殖などを支援する細胞(ニッチ細胞)を積極的に呼び寄せませんが、がん幹細胞は他の組織や体全体のことを考えずにニッチ細胞を呼び寄せ、操り、分化した娘細胞を増やせる環境を整えるという考え方です(図2)。
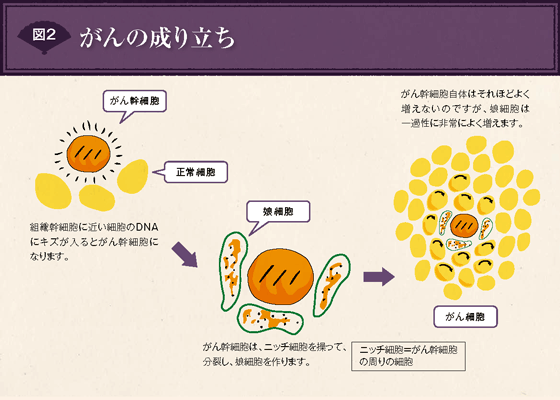
がん幹細胞自体にはそれほど増える力はありませんが、娘細胞は非常に良く増えます。そういう面では、先に挙げたハエの例えよりはハチの増殖に近いでしょう。がん幹細胞が女王蜂、娘細胞が働き蜂といったイメージです。
こうしたがん組織に従来型の放射線治療を行った場合、娘細胞から増えた働き蜂のような細胞だけが死滅して、悪の親玉であるがん幹細胞は生き残ることがあるようなのです。
がん治療を生き伸びた幹細胞は“冬眠”に入ります。乳がんの場合は冬眠期間が特に長いようですが、DNAに新たな傷が入ると目覚めて、再活性します。よみがえった幹細胞はまたニッチ細胞を呼び寄せ、娘細胞を増やしてがん組織を作っていきます(図3)。これが、がん再発の実態ではないかということが、最近分かってきました。
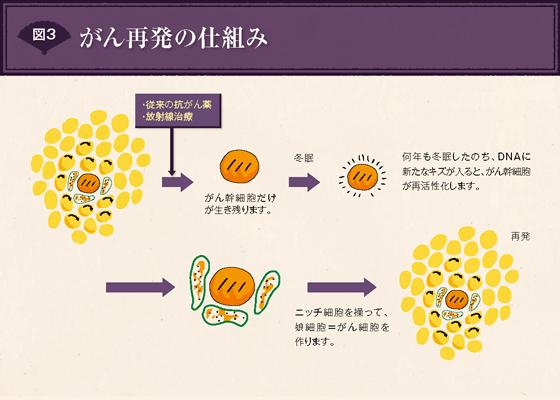
女王蜂の弱み―ニッチ細胞の役割を解明
ここでカギとなるのが、ニッチ細胞の存在です。がん幹細胞は、自分が生存・分裂するために周囲にさまざまなタンパク質を放出し、周辺の細胞を自分に都合が良いように呼び寄せ、操り、自分が体の中にすみつける環境を整えます。
ニッチ細胞はこの操られる側の細胞のことで、新しく血管を作る細胞、免疫を押さえ込む細胞、がん細胞の隙間を埋める間質細胞、娘細胞など、さまざまな細胞が含まれます(図4)。
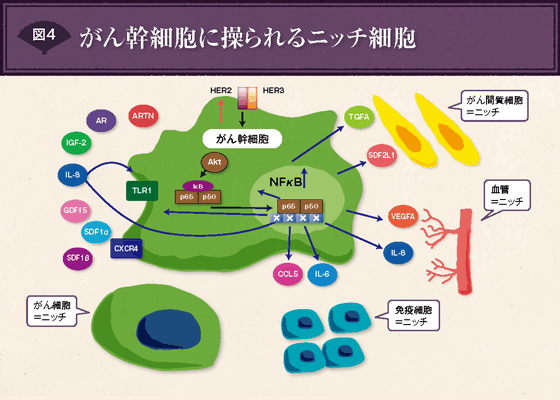
操られる存在ではありますが、ニッチ細胞なくしてがん幹細胞は体にすみつくことができません。つまり、従来の抗がん薬や放射線治療ではやっつけにくかったがん幹細胞の弱みが、ここにあることがようやく分かってきたのです。
がん幹細胞、あるいはニッチ細胞をターゲットにした治療ができるようになれば、がん再発の不安はなくなります。今、そうした治療法の開発に向けた研究が世界中で始められているところです。
(企画・制作:あなたの健康百科)






