第23回日本癌学会市民公開講座 講演3「肺がんの予防と治療はこんなに進んでいる!」
矢野 聖二 先生(金沢大学がん進展制御研究所腫瘍内科教授)
がんによる死亡第1位は肺がん、原因はやっぱりたばこ!
肺がんは日本人のがんによる死亡原因の第1位を占めるがんです。2012年のデータではがんで亡くなられた方は36万人超で、このうち肺がんによる死亡は約7万人。ちょうど5人に1人が肺がんで亡くなっている現状があります。
肺がんの一番の原因はたばこです。たばこの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれており、このうち200種類以上が有害物質、60種類以上が発がん性物質であることが分かっています。アンモニアやヒ素、ホルムアルデヒド、カドミウム、一酸化炭素、DDT、シアン、ダイオキシン、ニコチンと、体に悪いものばかり入っているのがたばこなのです(図1)。
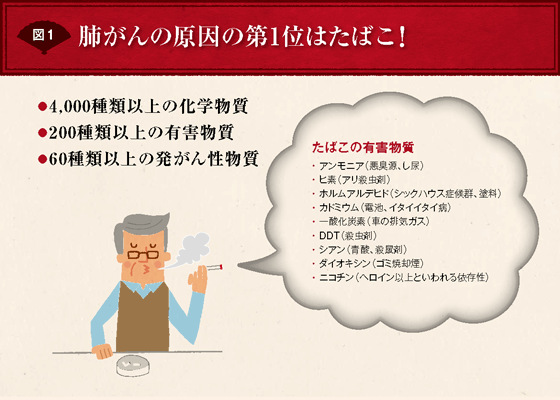
たばこを日常的に吸っている人では、肺がんを発症するリスクが吸っていない人の4.5倍、咽頭がんになるリスクは32.5倍に高まります。周りの人にも有害で、1日20本以上たばこを吸っている男性の妻は、吸っていない男性の妻に比べて肺がんになるリスクが1.91倍です。禁煙は本人だけでなく、大切な人を守るためにも必要なのです。
ここまで変わった肺がん治療
肺がんは小細胞がん、扁平(へんぺい)上皮がん、腺がん、大細胞がんに分類されます。このうち小細胞がんと扁平上皮がんの2つはタバコとの因果関係が強く、腺がんや大細胞がんはそれほど強くありません。
いずれのタイプでも、治療は(1)手術、(2)放射線治療、(3)抗がん薬や分子標的薬による化学療法―という3つの手段を総合的に用いて進めます。
がんが局所(限られた一部分)にとどまっている早期がんでは手術が最も確実かつ有効な治療法ですが、縦隔(心臓、食道、気管、大動脈・大静脈などがある左右の肺に囲まれ部分)に広がっている局所進行期には放射線治療を主体に薬による化学療法を併用、がんが転移している進行期であれば化学療法が選ばれます(図2)。
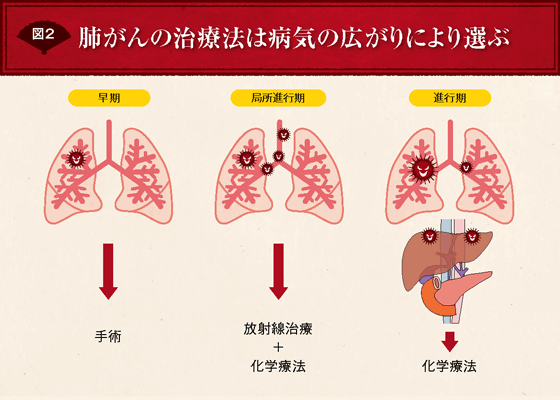
従来、肺がんの手術は早期でも30センチほど切開し、肺やリンパ節を大きく切除していたため、患者さんの負担が大きく、手術後には肺機能が低下してしまうことが問題でした。
しかし現在は、早期であれば内視鏡を使った胸腔鏡手術も可能になっています。肺の切除も切る部分を限ったり、楔状(けつじょう=三角形)に切ったりして、機能を温存できるようになりました(図3)。
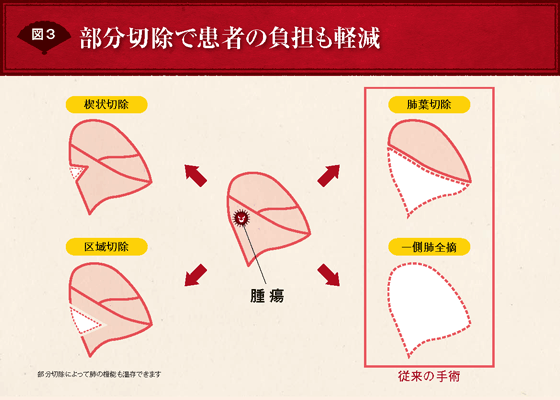
放射線治療も、定位放射線治療の登場によって大きく進化しています。この治療法は、放射線を出す機械が患者さんの周りをぐるぐる回って、ターゲットのがん細胞へ3次元で集中的に放射線を照射するものです。
従来の放射線治療では、がんのある部位全体に放射線を当て、中を焼き切るようにがん細胞を死滅させていたため、正常な細胞へのダメージも大きくなっていました。
定位放射線治療ではがん細胞だけに集中して照射できるので、正常な細胞へのダメージが少なく済みます。がん細胞の死滅効果も高く、早期肺がんであれば手術とほぼ同等の治療成績が得られるようになっています。
生存1年の壁破った分子標的薬
がんが進行し、胸水がたまったり、肺以外の臓器に遠隔転移したりしている場合には、化学療法が行われます。
1990年代まで、肺がんに対する抗がん薬は4種類しかありませんでした。その後、いわゆる第三世代の抗がん薬がいくつか登場しましたが、それらを複数使っても、進行肺がんの場合で生存期間が10~14カ月ほどにとどまるという壁がありました。その壁を打ち破る存在として期待されているのが、分子標的薬です。
肺がんとは、そもそも正常な肺細胞の遺伝子に喫煙などで傷がつき、異常が生じ、性格が変わってがん細胞になり、無制限に増えてしまう病気です。分子標的薬は、この異常が起きることで知られている遺伝子―上皮成長因子受容体(EGFR)や未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)―に作用する薬なのです。肺がんに対する分子標的薬は、現在5種類(ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブ、クリゾチニブ、ベバシズマブ)あります。
分子標的薬は、ターゲットとする遺伝子にピンポイントで作用し、正常な細胞には作用しないため、副作用が少なく抑えられます。この薬の登場によって、進行した肺がん患者さんの生存期間は大きく延びました。EGFR遺伝子に変異のある患者さんに分子標的薬を使って正しく治療を行えた場合、10年前の倍以上、30カ月ほども生存できるようになってきたのです(図4、5)。
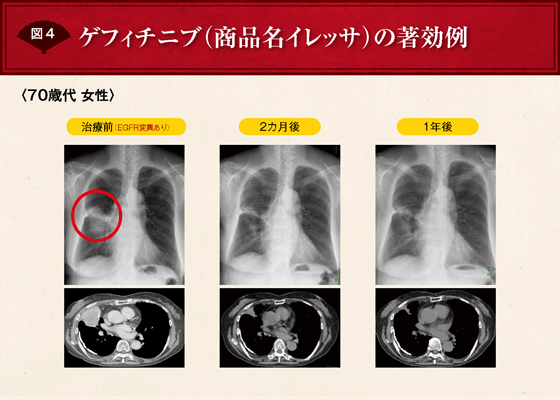
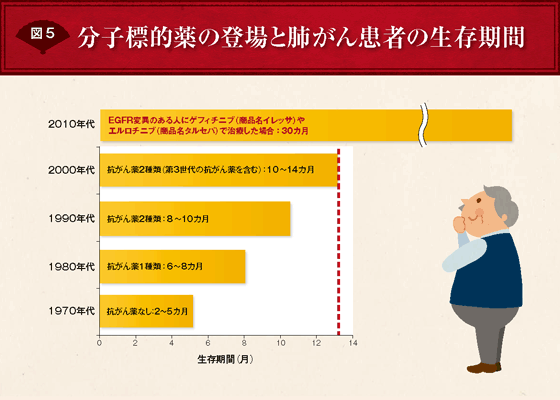
分子標的薬を使った研究や治療が進む中で、興味深いことも分かってきました。タバコを吸わないのに肺がんになった人で多く見られる遺伝子変異が見つかったのです。タバコとの因果関係が強くない腺がんでは、特にEGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子を持つ人が多く、そのうち8割で分子標的薬がよく効くことが分かってきています。
なお、分子標的薬が効くかどうかは検査である程度予測でき、検査費用は2万~6万円ほどです(健康保険加入者では自己負担はこの1~3割)。
分子標的薬にも問題はあります。まず挙げられるのは副作用です。基本的には正常細胞は攻撃しない薬ですが、EGFR遺伝子やALK遺伝子が発現している部分、例えば皮膚や肝臓、腸の粘膜などには作用してしまうのです。ゲフィチニブの場合、6割弱の患者さんで発疹や肝障害、下痢といった症状が報告されています。
症状は薬をやめれば2週間ほどで消えますが、間質性肺炎はまれに死に至るほど重症化することがあります。喫煙者や間質性肺炎にかかったことのある人で起こりやすく、主治医とよく相談する必要があります。
薬の値段が高い問題もあります。従来の抗がん薬による治療でも1カ月に15万~30万円ほどかかっていましたが、分子標的薬を使った治療では、薬によっては1カ月に70万円ほどかかります。健康保険や高額療養費制度が使えるとはいえ、分子標的薬は値の張る薬なのです。
もう一つ、ターゲットとなる遺伝子異常があっても、分子標的薬が効きにくい体質があるという問題もあります。近年の研究で、そうした患者さんにはBIMという遺伝子にも変異(多型)があることが分かってきました。
私たちは、こうした患者さんにリンパ腫の抗がん薬を併用すると、分子標的薬の効き目が高まることを明らかにし、臨床試験を開始しています。分子標的薬が効かなくなった患者さんに新たな選択肢を示せるようになれば、生存期間をさらに延ばせると期待しています。
(企画・制作:あなたの健康百科)






