第23回日本癌学会市民公開講座 講演2「外科治療の最前線――安全に膵がん手術を受けて頂くための術前対策」
太田 哲生 先生(金沢大学消化器・乳腺・移植再生外科教授)
薄っぺらく隠れたように存在する膵臓
膵臓(すいぞう)がんは、がんの中でも治りにくいがんです。治りにくい最大の理由は、早期診断が難しいからです。そもそも、膵臓がどこにあるかを知っている人はあまり多くありません。昔は解剖学者でもその存在を知らず、発見されてもちょっとした脂肪の塊と見なされていました。これは「五臓六腑(ろっぷ)」という言葉に膵臓が含まれていないことにも現れています。
膵臓は胃の後ろに隠れて、背中側にへばりつくように存在しています(図1)。薄っぺらい臓器で、医学が進歩した現代でも膵臓にできたしこりをレントゲンで映し出すことは困難です。膵臓にできたがんが診断されるときはすでに進行して、手術が長時間に及ぶことが少なくありません。
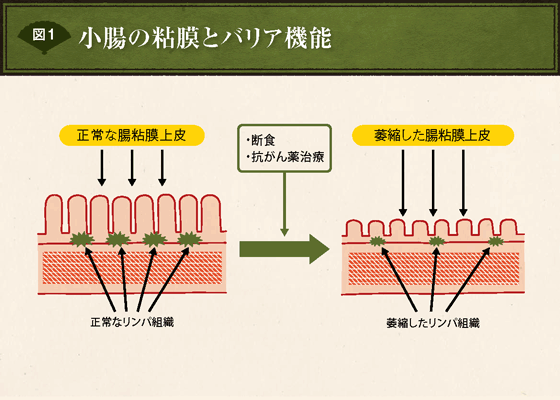
膵臓がんの手術をより安全に受けてもらうために、われわれは今、手術の前にある対策を行っています。それによって手術の後に発生する合併症を減らし、患者さんの回復を早められるのではないか、さらには免疫力を高め、がんの再発も抑えられるのではないか―そんな期待を込めて取り組んでいます。これは、膵臓がんに限らず、胃がんや大腸がんなど他のがんの治療にも行っています。
がん患者は腸が弱っていることが多い
その取り組みの一つが、小腸・大腸が本来持っている“腸能力”を高める工夫です。
正常な腸の粘膜には、「IgA」という炎症を抑える抗体がたくさんいます。IgAは血液や腸管、鼻水、唾液、母乳などに多く含まれ、それぞれの場所で細菌やウイルスへの感染予防に役立っているのですが、がんの手術で絶食したり、抗がん薬による治療で腸がダメージを受けたりすると、腸の粘膜とともにリンパ組織も萎縮してバリア機能が弱まってしまいます。
がん患者さんではこれに加えて腸内細菌叢(そう)、いわゆる腸内環境も乱れています。良い腸内環境とは善玉菌と悪玉菌がバランス良く存在する状態ですが、これが乱れると弱酸性の腸内環境が維持できません(図2)。
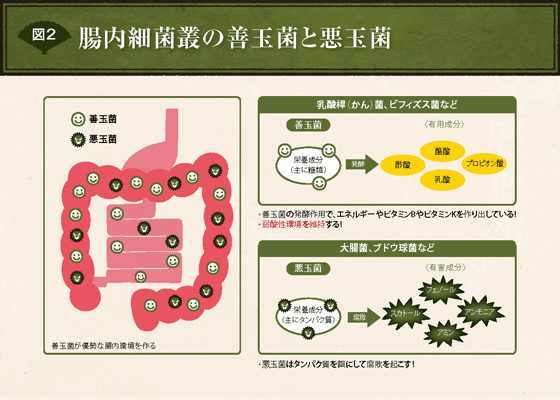
乳酸菌に代表される善玉菌が正常に醗酵している腸では、黄色でそれほど臭くない大便が出ます。反対に腸内に酸化物が多く異常醗酵していると、刺激臭の強い大便になります(図3)。
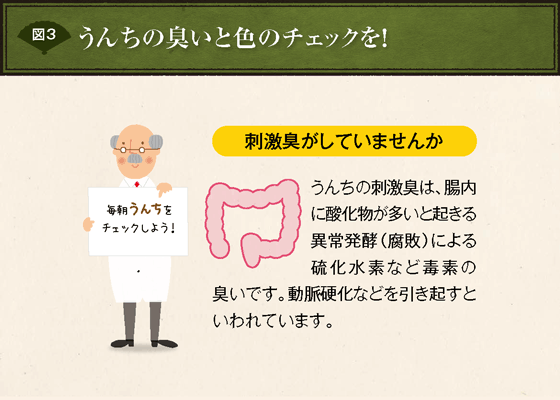
悪玉菌は体に良い水素も作る
大腸菌に代表される悪玉菌の存在も重要です。腸内で腐敗を起こす悪玉菌の中は良質な水素ガスを作り出すものがあり、作り出された水素ガスは速やかに血液の中へ取り込まれます。実はこれが、酸化ストレスの軽減や動脈硬化、生活習慣病の予防に役立つとして、世界中でたくさんの研究が行われているところです。
酸化ストレスや動脈硬化は、脳卒中や心筋梗塞といった病気になるリスクを高めるため、大きな手術はさまざまな抗酸化薬を使いながら行います。がん患者さんは腸が弱っていることが多く、手術の後の合併症を起こしやすい状態ですが、手術の前から腸内環境を整えることでも抗酸化作用が得られるのです。
小腸・大腸を強くするため、具体的に何をすればよいのか。われわれの病院では入院後から乳酸菌飲料やグルタミン、ファイバー、オリゴ糖の入った健康食品を食事と一緒に取ってもらっています。ドラッグストアや薬局などで手に入る比較的安価な健康食品で、がんであってもなくても、誰もが普段の生活の中で心がけることができる有意義な手術前の対策といえるでしょう。
長寿遺伝子のスイッチ入れるには?
聖路加国際病院(東京都)名誉院長の日野原重明先生は、103歳の高齢でありながら介護不要で、イキイキと仕事を続けています。健康作りのために65歳からは腹八分目を、現在では腹六分目を心がけた食事を続けているといいます。
この“おなかいっぱいにならない”という生活習慣に、実は「サーチュイン遺伝子」という長寿に関わる遺伝子を活性化する働きがあることが、15年ほど前から指摘され始めました。米マサチューセッツ工科大学のレオナルド・ガレンテ教授らが行った実験で、カロリー制限によって「NAD」という補酵素が増加し、サーチュイン遺伝子にまとわりついて活性化させることが分かったのです。
別の研究者が行った実験では、摂取するカロリーを30%減らしたアカゲザルと制限しなかったアカゲザルで、前者の方が糖尿病やがんになりにくく、全身の毛がつやつやして若々しい状態でいられることが分かりました(図4)(Science 2009; 325: 201-204)。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19590001
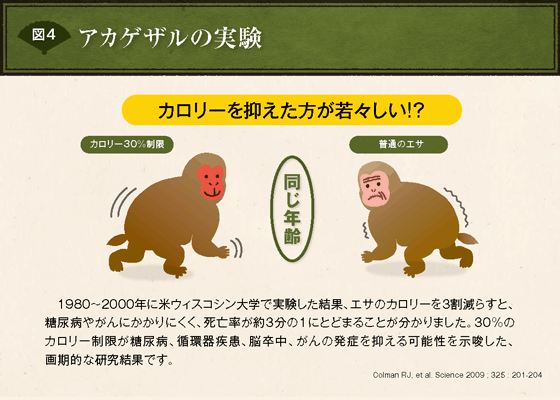
これは、30%のカロリー制限が糖尿病やがん、心筋梗塞、脳卒中の発症を抑えることを示唆した画期的な実験でした。満腹感のある生活をずっと続けていると老化が進みますが、ほどよく制限するとアンチエイジングになることが明らかになったのです。
長寿遺伝子を活性化するカギになるのは、軽いカロリー制限と運動です。がんになり、体力が落ちてからではできることに限りはありますが、長寿遺伝子を活性化した方がよいことに変わりはありません。短い期間でも手術の前にはできるだけ長寿遺伝子を活性化し、手術後も続ければ、再発、再々発の予防につながる―そう考えて実行することが重要なのです。
長寿遺伝子を活性化する薬も!
長寿遺伝子の活性化は、手術や抗がん薬の治療の前に薬で行うこともできます。例えば、メトホルミンという糖尿病治療薬を手術前の患者さんが服用すると、運動をしたのと似た効果を得ることができます。
脂質異常症の治療に使われるイコサペント酸(EPA)やスタチンも、体にさまざまな好影響を与える「アディポネクチン」というタンパク質の血液中の濃度を高める働きがあるとされています。高血圧治療に使われるアンジオテンシンⅡ受容体拮抗(きっこう)薬(ARB)という薬も、抗がん薬の効き目を高めるとされています。
手術後の回復を促す工夫として、スポーツの前後に用いられるアミノ酸のサプリメントを飲んでもらうこともあります。手術は激しい運動を行ったのと同じくらいに患者さんの体力を奪いますから、その回復を助けるという考え方です。
弱っている腸に対しても、グルタミンなどのアミノ酸を補給する方法で働きかけを行っています。手術後はこれまで、腸を安静にさせるために絶食するのが常識でしたが、今はその逆で、腸はやはり働かせなければならないという考え方が主流になっています。
こうした手術前の対策にどれほどの有効性があるのかについては、まだエビデンス(根拠となる研究結果)がありませんが、証明に向けた検討は始めています。腸を丈夫にし、免疫を高めることによって合併症を減らし、がんの再発も防ごうという取り組みを、外科医の視点から始めているところです。
(企画・制作:あなたの健康百科)






