日本癌学会・日本対がん協会主催 第22回日本癌学会市民公開講座 講演3「日本発のロボット手術開発へ:ガスレス・シングルポート・ロボサージャン手術」
木原 和徳 先生(東京医科歯科大学大学院腎泌尿器外科教授)
先端機器を身に着けて術者をロボット化
おなかにできたがんなどに対して、内視鏡と操作器具をいくつかの穴から挿入して行う腹腔(くう)鏡手術は、大きくおなかを切り開く開腹手術に比べて患者さんの体への負担を軽減させました。 さらに、ロボット手術は立体内視鏡、指のように関節の多い鉗子(かんし=物をつかんだり引っ張ったりする手術器具)、患者さんから離れた位置で操作するシステムを導入し、手術操作を行いやすくしました。
こうした中で開発されたのが、これまでのロボット手術の課題を克服することを目指し、コンパクトな先端ロボット機器を術者の身に着けて術者自身をロボット化し、1つの小さな穴から高度で安全な手術をしようというのが、日本発の「ガスレス・シングルポート・ロボサージャン手術」―二酸化炭素でおなかを膨らませることなく、過大な費用をかけずに、高度な操作を行うという手術です。
この手術では、術者(執刀医)は顔に図1のような「3Dヘッドマウント・ディスプレイ」を着けます。 このディスプレイは東京医科歯科大学大学院腎泌尿器外科と企業の産学連携で開発された器具であり、図2のように、術者に6つの視覚を提供します。 患者さんの体内の立体視、拡大視、全体的に俯瞰(ふかん)できる肉眼視、超音波などで操作を誘導する誘導視、手術チーム全員で同じ画像を見る共有視、MRI(磁気共鳴画像)やCT(コンピューター断層画像)などを同時に映し出す多画面視です。 誘導視では、内視鏡像と超音波像を併用して、裏にある血管や臓器を観察しながら、手術を安全・確実に進めることができます(図3)。
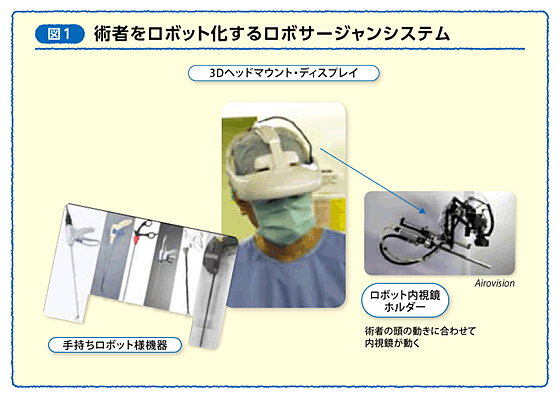
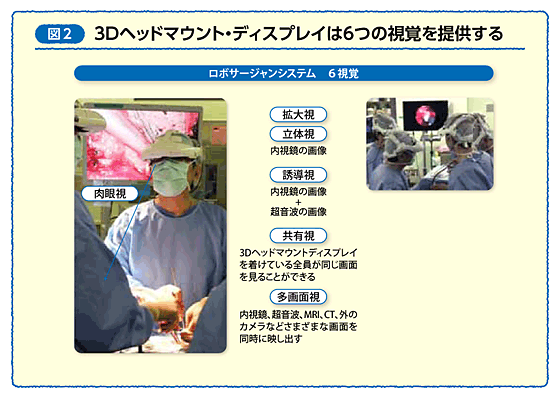
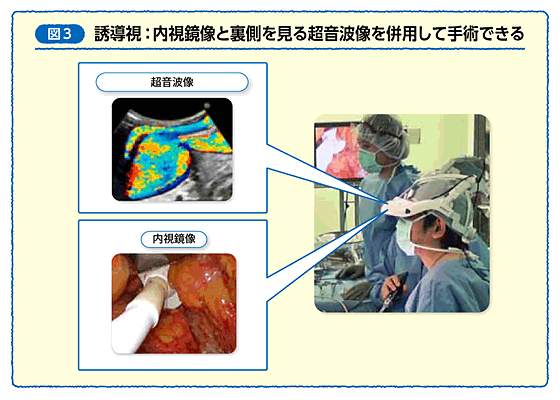
術者以外の手術参加者もこのディスプレイを身に着けて、手術情報を共有しながら操作を進められるほか、医学生らが着けて離れた位置で術者と同じ体験をすることができます(部分ロボット化)。
また、手には人の能力をはるかに超えた各種の先端機器を持ちます。 内視鏡は術者の頭の動きでコントロールすることが可能です。 空気圧で滑らかに内視鏡をロボット操作できる機器(Airovision)が開発されています。 これらの機器は、基本的に国産です。
ディスプレイ上の多様な画像は、機器を付加することにより、切り替え、拡大縮小、回転など自由度の高い操作を行うことができます(図4)。
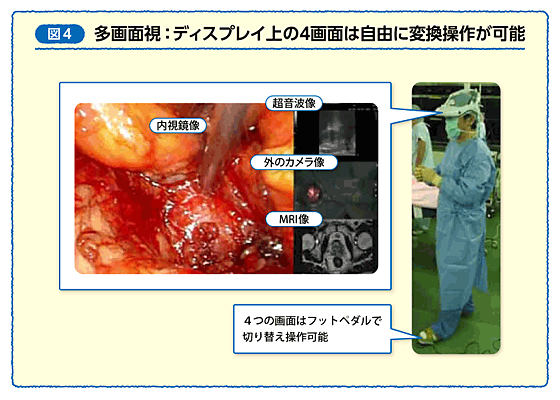
これまでのロボット手術の課題を克服する、もう1つのロボット手術という位置にあります。
小さな1つの穴から、おなかに優しい手術
開発を進めてきたこのロボサージャンシステムと、同じく開発を進めてきたガスレス・シングルポート手術を合わせ、全体をガスレス・シングルポート・ロボサージャン手術と呼んでいます。 ガスレス・シングルポート手術は、図5のように二酸化炭素を使わず(ガスレス)、小さな1つの穴(シングルポート)から行う手術。 過大な費用をかけず、臓器を守る膜(腹膜)に負担を掛けず、抗生物質(抗菌薬)をゼロあるいはごく少量に抑える手術でもあります。
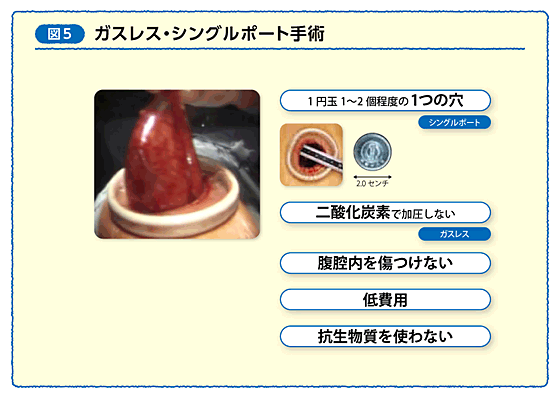
これらの各要素は、日本を筆頭に世界が迎える超高齢社会に適したものです。ガスレス・シングルポート手術は、ミニマム創内視鏡下手術と呼ばれて洗練が進められてきた手術の先端型ともいえます(先端型ミニマム創内視鏡下手術)。
おなかには風船のような腹膜腔がありますので、ここに二酸化炭素を注入して膨らませると簡単に広い手術空間を作ることができます。しかし、二酸化炭素で圧を加えると呼吸器系(肺など)や循環器系(心臓など)に負荷を掛け、麻酔医も細心の注意が必要になります。超高齢社会では、呼吸・循環系に障害を持つ患者さんがいっそう増加します。
また、膨らませた腹膜腔の中を手術操作することは、腸の癒着による腸閉塞のリスクを高めることになります。さらに、超高齢社会では、以前におなかの手術をしたことがある患者さん(すでに癒着を持つ患者さん)の増加も予測されます。同じ結果が得られるのであれば、二酸化炭素を使わず、おなかの中を操作しないことが望ましいと考えられるのです。
手術を行う穴を1つにするということも、目指すところは同じく患者さんの体に負担を掛けないことです。
現在の腹腔鏡手術やロボット手術では、おなかにいくつもの穴を開け、そこから器具を挿入して手術操作を行い、最後に穴を広げて、切り離した臓器やその一部を取り出すというコンセプトですが、シングルポート手術は、この取り出す穴だけで手術を完了しようというもの。
シングルポートのサイズは、副腎摘除や腎臓の部分切除では、2~3センチ台(1円玉1~1個半程度)のことも多く、腫瘍の大きさや位置、深さ次第で、1~2センチ広げることもあります。 腎臓の全摘除では、腫瘍とともに腎臓が辛うじて取り出せるサイズ、1円玉2~2個半程度の穴が多く使われます。 前立腺の全摘除では、1円玉2個分ほどの穴から前立腺が取り出されます。 腎臓と尿管と膀胱(ぼうこう)の一部を連続して摘除する場合は、腰の1円玉2個程度の穴と下腹部の1円玉1個程度の穴を使って全体を切り離し、腰の穴から全体を取り出します。 これらの手術は、腹膜内を操作せずに行われます。
また、シングルポートから手術空間の洗浄も十分にできますので、手術に際して感染予防に用いる抗菌薬をゼロあるいは極少量にすることができます。 これにより私たちの病棟では耐性菌はゼロに近くになり、薬剤による患者さんへの副作用も回避することができるようになりました。
「支払い可能な費用」と「最高の質」の両立を目指して
世界の主要国は、急速に超高齢化に向かっており、中でも日本は世界に先んじてすでに超高齢社会となり、勢いを加速させながら今後も先頭を走り続けると予測されています。 そのため、医療を必要とする人口は急速に増加しており、ここに就労人口の減少、医療の高額化が重なる状況になっています。
一方、国民医療費は国の税収にほぼ匹敵する額に達しており、さらに毎年1兆円ずつ増加し続け、国の負債は1,000兆円を超えたと報道されています。 今、求められる医療は、「支払い可能な費用」と「最良の質」を両立する医療でしょう。 ガスレス・シングルポート・ロボサージャン手術は、この両立を目指して開発、確立が進められています。
手術を含む医療のロボット化は時代の流れですが、これまでのロボット手術には、①極めて高い購入・維持・使い捨て器具コスト、②二酸化炭素による加圧、③多数の手術穴、④大きな機器サイズ、⑤触覚の欠如、⑥十分な俯瞰視の欠如、⑦頭の位置の固定、⑧術者は患者から離れている、⑨海外一社の独占商品―のような課題があります。 ロボサージャン手術はこれらの各項目を克服する潜在能力を持つものと考えられます。
この手術は優れた初期成績を挙げており、米国や欧州の学会で報告し、欧州の学会の手術ビデオライブラリーに収載され、高い評価を受けています。 現在はさらに洗練、高度化が進められており、これから超高齢社会を迎える世界の患者さんに、身体的にも経済的にも負荷を最小にする、日本発のロボット手術として育つことが期待されます。
(企画・制作:あなたの健康百科)






